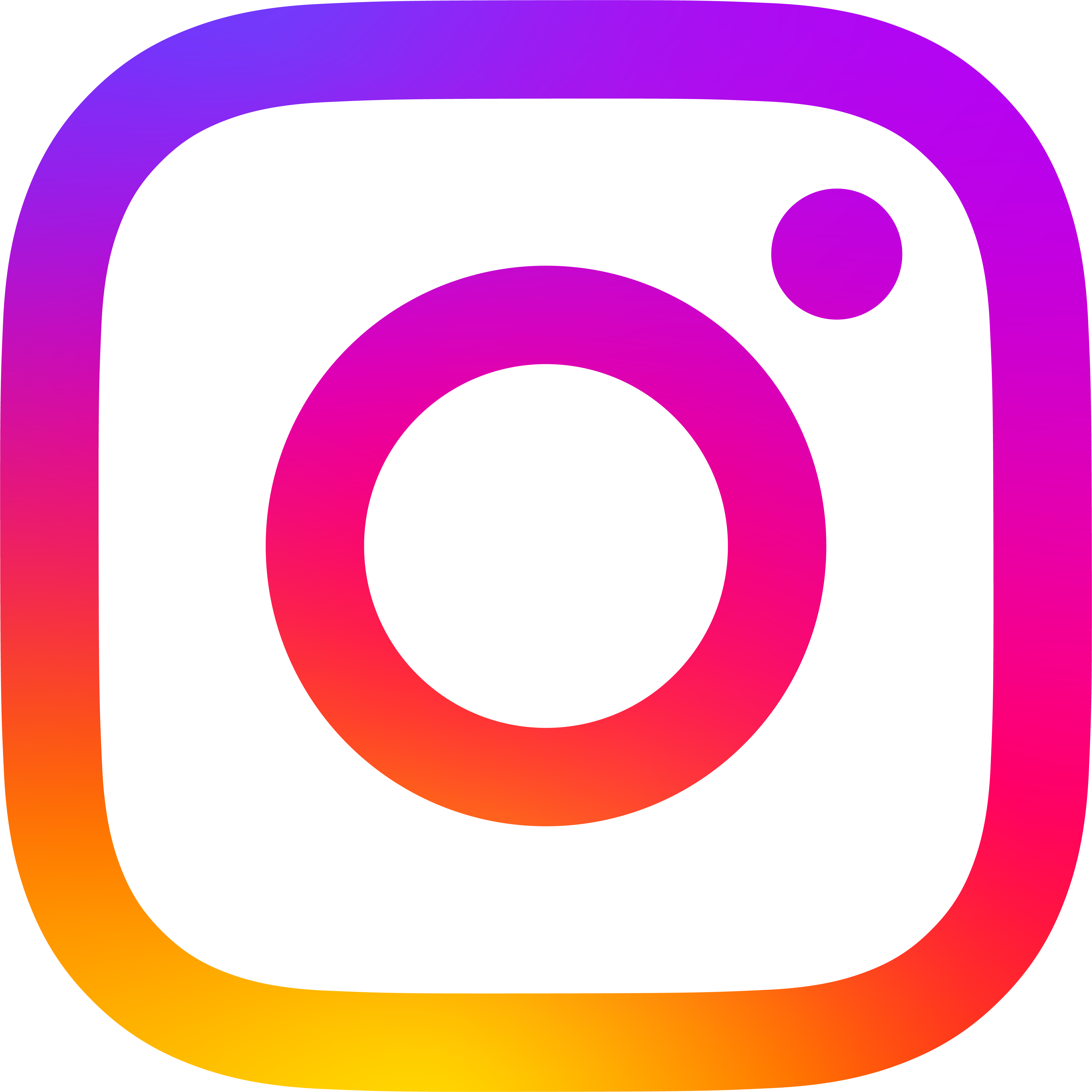2025.09.29 | レポート | 未来構想Lab
【講義レポート】未来デザイン思考ワークショップ
未来のキャリアや仕事を考えるだけでなく、
「どんな自分になりたいか」を言語化し、行動に繋げる。
未来デザイン思考ワークショップを詳細レポート!
「未来デザイン思考ワークショップ」とは
「未来デザイン思考ワークショップ」では、デザイン思考やキャリアデザイン学、心理学・脳科学などの知見を活用しながら、「自分の未来を創り出す力」を育むことを目的としています。単なる就職活動の準備ではなく、自分の価値観や経験をもとにした思考法・行動力を養う内容となっており、社会に出てからも長く役立つ学びが詰まった授業です。
計14回の講義の中で、受講生はさまざまな思考法を学びながら、自分の感情や価値観、過去の経験、そして想像する未来の姿を言語化してきました。さらに、自分の未来に近い社会人へのインタビューを実施し、擬似的な未来体験を行いました。
そして、7月28日 (月) に行われた最終講義では、受講生による「未来ビジョン」の発表会が開かれました。講義を通じて明確化された自分の価値観や過去の経験、インタビューで得た学びに基づいて、社会人3年目までの未来ビジョンを発表者がそれぞれ語りました。最終講義では代表として、4名の学生が発表を行いました。教室には多くの受講生が集まり、発表に耳を傾けていました。なお、発表者以外の受講者も動画形式で自身のビジョンを提出することが本講義の課題となっています。
講義を通して得た学びを共有

どの発表者も、現在の自分の立ち位置を見つめながら、社会人3年目までのプラン、そこに至るまでの「冒険プラン」、未来に向けた「プロトタイプ(試作行動)」を言語化し、具体的に語っていました。
例えば、ある発表者は、研究や教育の道を志す一方で、友人関係や健康面にも意識を向け、「自分を大切にした生き方」を模索していました。発表の最後には「これまで考えていたことが、授業を通してつながり、明確になった」と語っていたのが印象的でした。
また、別の発表者は、具体的な就職先を目標の一つに掲げ、そのためにクリアすべき課題を具体的に整理していました。実際に目指す就職先で働く人にインタビューを行い、助言を得た経験も共有。発表の最後には、「これまで一つのプランAだけを推し進めてきたが、今は定期的に振り返り、プランを立て直すこともできると学べた」と語っていました。
他の発表者では、過去に取り組んだ図書館や公民館でのボランティア活動が、現在の価値観や人生観、仕事観に繋がっていると語られていました。また、図書館司書へのインタビューを通じて、学ぶべきことや現場の課題にも気づいたそうです。「何かになりたい」ではなく「どんな自分になりたい」を考えることの重要性に気づき、「それが明確であれば、いつからでもキャリア形成はできる」と締めくくっていたのが印象的でした。
最後の発表者は、「人生を楽しむこと」を軸に据え、自分自身の価値観や仕事観を明確にすることで、楽しみながら生きるというスタンスを提示しました。講義を通して、自分が本当にやりたかったことを明確化できたと振り返っていました。
4名の発表を受けて、松下先生は「どんな職業になりたいか」ではなく、「どんな人物になりたいか」という視点が全員の発表に共通していた点を評価。「具体的な職業像にこだわると、その通りにならなかった時に自信を失いがちだが、人物像を軸にするとブレない」とコメントしていたのが印象的でした。
「ライフデザインは授業であって授業ではない」
自分を深く見つめるプロセスが、人生をデザインする意識を育む

講義全体を通じて、体験の言語化や価値観の可視化を行い、自分を深く見つめるプロセスが丁寧に積み重ねられてきたことを感じました。また、回を追うごとに、受講生は「仕事とは何か」「人生とは何か」「未来に向けて自分はどうありたいか」を考え、最終的にはそれぞれの「冒険プラン」を描いていました。
この授業の魅力は、未来の「キャリア」や「仕事」を考えるだけでなく、それを通じて「どんな自分になりたいか」を言語化し、行動に繋げていくこと点にあると思います。社会人3年目までを見据える構成もユニークで、「入社」がゴールになりがちな学生にとって、より長期的な視野で人生を捉える機会となるでしょう。
また、多様な価値観に触れ、実社会で活躍する人々のリアルな声を聞く経験は、未来への具体的なステップを描く上で大きなヒントとなるでしょう。「ライフデザインは授業であって授業ではない」という松下先生の言葉のとおり、自分の人生をデザインする意識を育ててくれる貴重な時間でした。